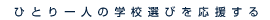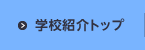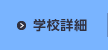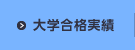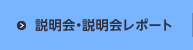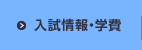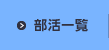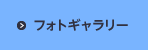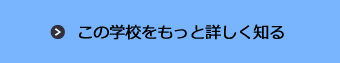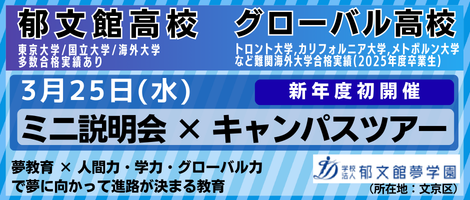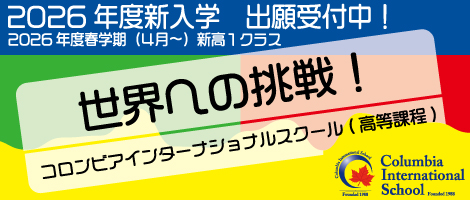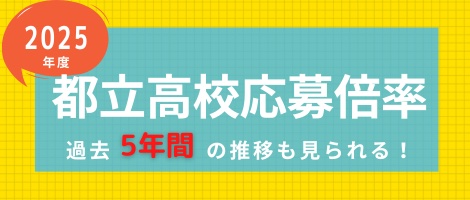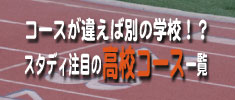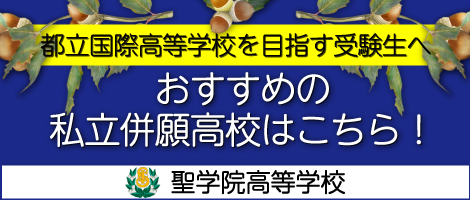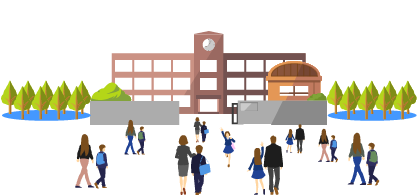スクール特集(武蔵野高等学校の特色のある教育 #1)

大学レベルの探究活動や海外研修も充実! 3年生が語る「特進ステージ」の魅力
武蔵野高等学校では、進路に合わせて選べる「進学ステージ」と「特進ステージ」という2つのステージ(コース)を用意。今回は「特進ステージ」の生徒に話を聞いた。
武蔵野高等学校では、それぞれが目指す道に合わせて自分を表現できるように「進学ステージ」と「特進ステージ」という2つのステージ(コース)を用意。「進学ステージ」は、基礎的な学習を繰り返しながら、部活動や学校行事にも力を入れて学校生活を充実させる。一方、「特進ステージ」は、難関大学現役合格を目指し、より高度な学力を育成。「特進ステージ」で経験した探究活動や海外研修を大学での学びにつなげようとしている3年生と、「特進ステージ」3年担任の多田結先生(進路指導部部長)に話を聞いた。
<話を聞いた3年生が参加したプログラム>
Hさん(高3):ウアイヌコロ会議、セブ島集中語学研修
Aさん(高3):ウアイヌコロ会議、セブ島集中語学研修
Iさん(高3):カナダ海外研修(1年次、2年次)
Sさん(高3):カナダ海外研修、セブ島集中語学研修
大学教授の指導が受けられる探究活動
校訓として「他者理解」を掲げる同校は、社会に出てから必要とされる人材の育成を目指し、勉強面だけでなく、生きていくために必要な力を身につけることも重視。「特進ステージ」では、大学進学を目指す中でそれぞれの可能性を見つけていけるように、探究活動や海外研修といった様々なプログラムを用意している。「特進ステージ」が「進学ステージ」と大きく異なる点は、受験を意識した授業設計と7限目講習だ。主要5教科の授業を効率的に進め、通常授業のあとに7限目講習を実施。難関大学合格に向けてより実践的な問題にチャレンジしたり、併設校である武蔵野学院大学の教授による授業が受けられる。
「週1回、系列大学の教授に授業を行っていただきます。グループディスカッションをしたり、巣鴨で地域の課題を見つけたりするフィールドワークを行うなど、大学のゼミのような感じです。1・2年生合同で行い、教員も2学年合同で7~8人が担当するので、多様な考えに触れる機会にもなっています」(多田先生)
大学教授による講習の前期は、死刑制度の是非や選択的夫婦別性制度などに関するディベートや、軍事問題について考える講義を受講。後期はそれぞれが課題を見つけてグループワークを進め、教授の前でプレゼンを行う。
「教授に見ていただく前に、指摘されそうなところを想定して修正したものをプレゼンしましたが、こちらの想定を超えた角度からの指摘があり、大学レベルと高校レベルの差を感じました。自分たちはどう考えたかを重視するなど、視点も違うなと思います」(Hさん)
Aさんも、プレゼン後のフィードバックで視点の違いを感じたと振り返る。
「5年後にどんな機械が普及しているかというテーマで、AIのメリットやデメリットについて考えてどのような暮らしになるかプレゼンしました。限られた知識の中で自分なりに考えましたが、プレゼン後のフィードバックで、『AIの責任はどう取るの?』と質問されたので、そのような見方もあるのだと気づかされました」(Aさん)
Iさんは、視点の違いを感じたと同時に、スキルが身についたことも実感しているという。
「1つのテーマに対するアプローチの仕方、課題についてちゃんと本質を知ってからどう解決していくか考えることなど、探究の基本を学べました。プレゼンのスライド作りでは、グラフの扱い方や根拠づけをきちんとできるようにするなど、スキルが身についたと思います」(Iさん)
Sさんも、スライド作りなどで学びがあったことが実感できたそうだ。
「スライドを作るときに目次を出した方がいいことや、引用元を書いた方がいいことなども知ることができました。教授は『あなたたちはどう思うの?』と聞いてくださり、それぞれの生き方や考えも大事にしてくれていると感じます」(Sさん)
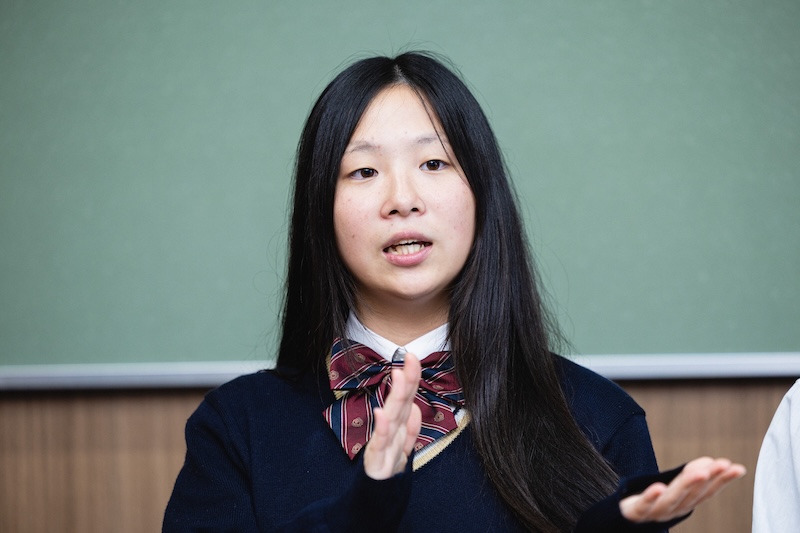
▶︎Hさん

▶︎Aさん
共生社会について考える「ウアイヌコロ会議」での学び
探究活動の一環として、今年1月に北海道で開催された「第1回 ウアイヌコロ会議」に「特進ステージ」の生徒4名(Hさん、Aさん他2名)が参加した。全国から14校の高校生が参加した同会議は、アイヌ民族の多様な歴史や文化に触れ、「共生社会」の実現について考えるために今年初めて開催された2泊3日のプログラムだ。
「現地に行く前に事前学習としてリモート会議に2回参加して、無意識の偏見や思い込みが相手を傷つけてしまうマイクロアグレッション(小さな攻撃)の経験などについて話し合いました。1日目に共生社会について事前に考えたことを共有する時間があったのですが、それぞれの経験や街中で見かけた事例などもいろいろあって、学んだ環境が違うと考え方も違ってくることを実感しました。先住民の方からアイヌの文化について学ぶ時間もあり、もっと深く学びたいという気持ちになったので、今も浅草にあるアイヌ文化交流センターで開催されている公開講座に定期的に参加しています」(Hさん)
同会議では、アイヌ文化だけでなく、オーストラリア先住民族の文化紹介もあった。
「マイクロアグレッションに気をつけながら、アイヌやアボリジニの方と交流しました。私はハーフなのですが、どの国のハーフか聞かれることはあまり気になりません。一方で、先住民の方たちは人種について聞かれることを気にする人が多いと初めて知りました。民族の違いなどにより、相手を傷つけない接し方について考えるきっかけになったと思います。お互いを認め合えるインクルーシブな環境を作ることが大切だと学び、現状を知ってどう改善すればよいか考えるための1歩を踏み出すきっかけになりました。全国から集まった高校生のいろいろな考えを聞くことができ、自分の凝り固まった視点にも気づかされました」(Aさん)
会議に同行した多田先生は、他校の生徒からもよい刺激を受けたという。
「関西圏の生徒たちはとてもフレンドリーだったり、地域による生徒の違いも感じました。 北海道の生徒たちは、ホスト校として道外の生徒たちを一生懸命に受け入れようとしてくれたり、地元を紹介してくれたりして、いろいろな面で勉強になる3日間だったと思います。会議に参加後、現地に行けなかった生徒たちにもプログラムで体験したことを共有しました。この会議がきっかけでウポポイ(民族共生象徴空間)の方が本校に来てくださり、講演や民族衣装の試着体験、伝統楽器の演奏体験など、アイヌ文化に触れる機会ができたので、今後もさらに関係を深めていきたいと思っています」(多田先生)

▶︎ウアイヌコロ会議
カナダ海外研修(高1・高2 希望制)での成長
「特進ステージ」では、総合型選抜などにも対応できる様々な活動に取り組んでおり、海外研修に参加する生徒も多い。文化体験がメインのカナダ海外研修は、1家庭1人でホームステイをしながら現地の学校に通う2週間のプログラム。Iさんは、高1のときに参加して、再挑戦したいという思いがあって高2でも参加した。
「もともと異文化に興味があったので、1年生のときは楽しそうだなと思って参加しました。実際に行ってみたら、言葉の壁や文化の違いが思っていた以上にあって、思うようにコミュニケーションができなかったんです。悔しさもあって、もっとコミュニケーションが取れるようになりたいと思うようになりました。帰国後に英会話スクールに通ったりしてコミュニケーション力を上げて、2年生のときにもう一度カナダ研修に参加しました」(Iさん)
1回目は必要最低限のことしか話せなかったので、相手の気持ちもよくわからず、不安や嫌な気持ちにつながってしまったという。しかし、2回目は自分から話そうと決めて行ったので、より多くの人と交流できて、1回目より楽しい思い出にすることができたとIさんは振り返る。
「現地の学校に通ったときに、私のぎこちない英語でも聞こうとしてわかりやすく話してくれたり、自分たちの文化を伝えようとしてくれる優しさなども感じられたりして、よい刺激を受けました。1回目は言葉の壁が厚かったので、そういったことを感じる余裕がなかったのだと思います。内気な性格だったのですが、相手のことも理解しながら自分のことを話すことの大切さを学べたので、2回行けてよかったです」(Iさん)
多田先生から見ても、Iさんは大きく成長したという。
「同じ研修に2回参加する生徒は珍しいですが、Iさんは2回行ったことで大きく変わったと感じます。1年生の最初は、こんなに話せる生徒ではありませんでした。今では前に出て行く場面も多くなってきたので、彼女にとって本当によい経験になったのだと思います」(多田先生)

▶︎Iさん

セブ島集中語学研修(高1~高3 希望制)で楽しむ英語
夏休み中にフィリピンのセブ島で実施する語学研修は、全寮制の学校に1週間入学してマンツーマンの授業などを受ける集中プログラム。楽しく学べるプログラムなので、英語が得意ではなかった生徒も帰国する頃には苦手意識がなくなっているという。1年次にカナダ海外研修に参加したSさんは、2年次にはセブ島の研修に参加した。
「カナダ研修を経験してもっと話せるようになりたいと思っていたので、機会があるなら挑戦したいと思ってセブ島の研修にも参加しました。寮生活では、子どもから大人までいろいろな国籍の人と交流できて楽しかったです。先生は私が言いたいことを上手に引き出してくれて、踊ったりゲームをしながら英語を話したので、集中授業でも全く苦ではありませんでした。どんどん話せるようになって、自分はちゃんと英語を話せていると実感できて嬉しかったです」(Sさん)
初めての海外体験がセブ島研修だったというHさんは、自分の発音が相手に伝わらないことを痛感し挫折しそうになったという。そんなときも、SさんやAさんらの仲間がいたからなんとか頑張れたと振り返る。
「初めての海外研修でしたが、1人でホームステイではなく、みんなにフォローしてもらえる寮生活でよかったと思っています。みんなの優しさにも触れて、英語に対する興味も増してもっと学びたいと思うようになりました。英語で伝えようと本気で頑張ったので、帰国したときは、日本語が出てこないぐらいだったんです。それぐらい成長して、頑張れたと感じられる経験でした」(Hさん)
中学生のときはどちらかというと英語が苦手だったAさんは、高校入学後に英語が好きになりつつある途中でセブ島研修に参加したという。
「マンツーマンでしたが先生は盛り上げ上手で、緊張せずに話せる距離感で中学英語なども使ってわかりやすく教えてくれました。授業外でも気さくに声をかけてくれたので、先生というよりパートナーというイメージです。この研修でますます英語が好きになり、英検の勉強なども頑張れるようになりました」(Aさん)

▶︎Sさん

「特進ステージ」での学びから見えてきた将来像
高校3年間で経験した探究活動や海外研修などを通して、4人それぞれ大学で学びたい分野も見えてきた。Hさんは、1月に参加した「ウアイヌコロ会議」も大きく影響したという。
「私は高校の英語教師になりたいと思っています。海外研修での経験でボディランゲージも大事だと実感したので、文法だけでなくそういったコミュニケーションも教えられる先生になりたいです。ウアイヌコロ会議に参加してアイヌ文化についてさらに深く学びたいと思ったので、北海道の大学への進学を考えています。大学でも留学して、自分の経験すべてを伝えられる教師になりたいです」(Hさん)
入学前は英語がそれほど得意ではなかったと語っていたAさんは、英語を使う仕事がしたいという夢を持つようになった。
「高校で英語が好きになり、語学研修も経験して、英語を使う職業に就きたいと思うようになりました。外資系企業に就職して、日本と相手の国それぞれに必要なものを考えたり、お互いの国を知っていくことに関わったりしたいです。探究活動を通して学んだいろいろな視点を参考にして、大学のゼミでも自分の意見を発していきたいと思っています」(Aさん)
Iさんが探究活動を通じて関心を持つようになったのは、街づくりや観光に関わる分野だ。
「総合型選抜のレポートとして取り組んだ探究活動では、巣鴨の現状を知るために何回も街を歩いて、自分の視点で魅力や課題を考えました。自分の視点だけでなく、観光客や商店街の人などにもインタビューをして、解決策を提案してまとめています。これを大学での学びにもつなげて、地域や社会の課題を見つけてそれをどう改善していくかを考えていきたいです」(Iさん)
Sさんは、海外研修などの経験から、ホテルや空港で働きたいと思うようになったという。
「カナダやセブ島での経験を通して、私は人と接することが好きなのだと感じました。修学旅行やオープンキャンパスで沖縄へ行って、沖縄の空気感や時間の流れが自分にあっていると感じたので沖縄の大学への進学を目指しています。沖縄では米軍基地問題があったり、ホテルがたくさんあるので大学の授業でホテル研修などもあり、私が学びたいことがたくさん学べる環境です。いろいろな人と出会いながら、おもてなしの心を大事にして成長していける職業に就いて、後悔しない人生を送りたいと思っています」(Sさん)
<取材を終えて>
探究活動に取り組む中で、大学教授からのフィードバックがもらえることは非常に大きな成長につながると感じた。「特進ステージ」の生徒は、探究活動などで取り組んだことを活かして、約7割が年内入試で進学するという。インタビューした4人それぞれの経験が進路につながっているが、特に今年参加した「ウアイヌコロ会議」がHさんの進路に大きな影響を与えていたことが印象的だった。